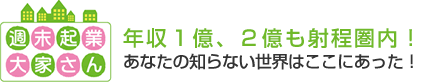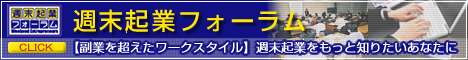【第3回】不動産投資のロードマップ
こんにちは。株式会社日本資産総研コンサルタントの大野晃弘です。
先日の週末起業フォーラム秋の感謝祭では、足元の悪い中、「大家で起業!不動産投資セミナー」にお越しいただき誠にありがとうございました。
予想を超える人数で参加者の方には窮屈な思いをさせて申し訳ございませんでした。
次回は広い場所できるよう対応してまいります。
今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。
さて、今回のテーマは、『不動産投資のロードマップ』です。第1回のコラムで図示したものを再度確認しながらご説明いたします。
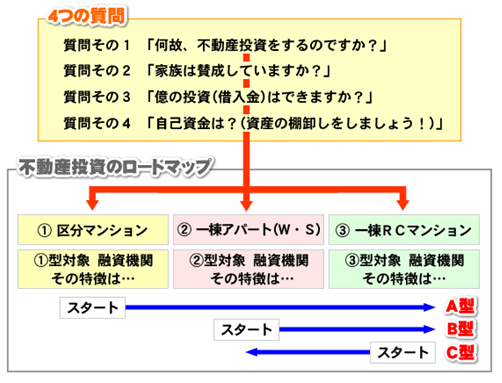
※Wは木造、Sは軽量鉄骨造、重量鉄骨造、RCは鉄筋コンクリート造を表しています。
以前にも申し上げましたが、私は弊社のセミナーや相談会で多くの投資家様とお話する機会があります。
ご相談内容は幅広く「どのような本を読めば良いのでしょうか?」といった初心者の方から、既に複数棟お持ちの方の「今後どのように資産を増やしていくのが得策か?」といったセミプロに近い方まで数多く対応しております。
既に複数の収益物件を保有している方の傾向を大別すると、以下の3パターンになります。
-
A型
区分マンションの複数戸の購入から始め、次に一棟アパートや一棟マンションを購入していく -
B型
積算評価※が高い一棟アパートを購入し続け、いずれは一棟RCマンションを視野に入れる※積算評価:金融機関が融資をする際の物件評価(土地・建物の合計金額)
※積算評価の簡易算出方法については今後コラムにて掲載予定です。 -
C型
一棟RCマンションを購入し続け、いずれはリスク分散として、一棟アパートを視野に入れる
最近は最初から一棟マンションを購入するC型を選択する方が非常に多く、実際に私の直近の取引事例は一棟RCマンションがほとんどです。
とは云え、皆さま各々に年収や自己資金が違いますので、身の丈にあった投資手順をお勧めします。
下の表は、区分マンション、一棟アパート、一棟マンションのメリットとデリット等について、代表的なものを簡単に整理したものです。
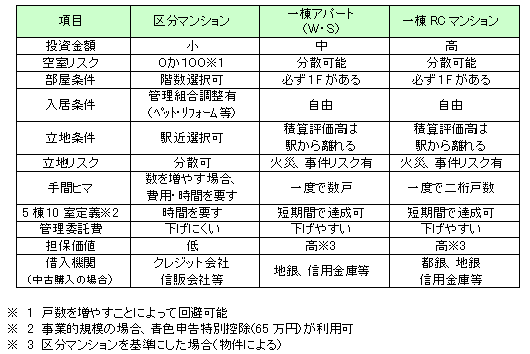
他にもありますが、物件毎のメリットとデメリットを理解し、自分の投資スタイルにあった物件からスタートすることをお勧めいたします。
ワンポイントアドバイス
賃貸経営の事業的規模
不動産業以外の事業も合わせておこなっている場合、賃貸規模に関わらず、事業的規模に該当します。サラリーマン大家さんの場合は、投資の規模が形式基準で5棟10室換算を満たしている必要があります。
例えば、アパートの場合は、1棟所有していてその貸室数が10室であれば事業的規模に該当。1棟貸家(戸建)の場合は、5棟所有して賃貸していれば10室相当(5棟×2室)と計算され事業的規模に該当します。
ただし、これらは形式判断ですので高額賃貸料を収受できる環境の場合、1棟のみの賃貸(1棟マンション)でも事業的規模の判断となるケースもあります。
事業的規模に該当している場合
個人経営の場合は、不動産賃貸経営の事務所を自宅に設置しているケースが多いのが現状です。家事経費との振り分けの問題が生じる例として、自宅・家賃・水道光熱費・通信費・車両費・旅費交通費などが挙げられます。
これらの振り分けは、税務上『合理的な基準』でおこなわれていれば特に問題は生じません。合理的な基準とは、税務署側を納得させる説明ができる基準といえます。
事業的規模に該当しない場合
事業的規模でない賃貸経営の場合、厳密に言いうと経費制限があります。
事業的規模に該当しない場合に認められる経費は、不動産収入を得るために生じた「直接経費」のみとなります。
「直接経費」とは、減価償却費・借入金利子・固定資産税・物件の管理費(物件に係る水道光熱費も含む)のことを指します。