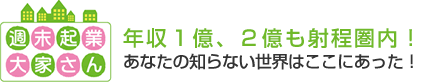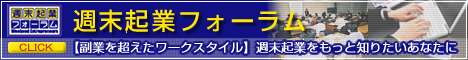不動産投資の初心者が知っておきたい減価償却とデッドクロス 【税金コラム03】
このコラムは、不動産投資専門税理士の志賀公斗先生に行ったインタビューをもとに作成しております。
不動産投資家が怖がるデッドクロスとは?
——デッドクロスって何ですか?
志賀:不動産投資のデッドクロスというと、何かものすごいヤバいものだというイメージがありますが、そんなことはありません。デッドクロスとは減価償却費と元金返済のバランスが逆転した現象のことをいいます。
サラリーマン大家さんの多くは、月額の返済額が一定の元利均等返済を選んでローンを返済していきます。家賃収入と返済額は一見、同じように推移しますが、税金の計算上は返済のうち利息しか経費に計上することはできません。つまり、ローンの返済が進むに従い、元金の割合が大きくなるので税金計算上は利益が出てきてしまうということになります。
一方、建物や設備といった減価償却資産は、一括して経費にすることができません。その資産の耐用年数に従って、その年の経費にできる金額を計上していきます。それが減価償却費用といいます。この減価償却費用は、当たり前のことですが、年を経るごとに減っていきます。不動産投資におけるデッドクロスとは、ローン返済の元金部分が多くなり、経費が計上できる割合が少なくなる。一方で、減価償却費用も経費計上ができなくなる。利益が増えているわけではないのに、税務上の利益が出て負担がダブルパンチで増える現象のことをいいます。
——なるほど。よくわかります。
志賀:どんな収益物件でもデッドクロスは訪れますし、定率法という減価償却費用を初めの年に多く計上する方法では、デッドクロスが早く訪れることになります。そんなに心配することはありません。現金の流れを管理するサラリーマン大家さんは多いのですが、税金の流れを管理している方は少ないから、ちょっと気をつけましょうということですね。では、なぜデッドクロスが注目されているのかというと、それには理由があるのです。
——デッドクロスが注目される理由を教えて下さい。
志賀:不動産会社や不動産コンサルタントは仲介手数料で利益を得ています。彼らは、手元に収益物件があれば、売りたいと思いますし、収益物件を持っている人には、売ってもらいたいと思います。不動産仲介したいわけです。「デッドクロスが近いので売りましょう」というのは、実はサラリーマン大家さんを儲けさせようと思って言っているわけではなく、不動産業者が儲けたいからそう言っているに過ぎません。過剰に怯える必要はなくて、家族に給料を出すとか、経費を使うとか、デッドクロスをなるべく後に持っていく方法はいくらでもあるのです。不動産会社は売り物件がないので、そうやって、デッドクロスの近い大家さんに、物件を売って欲しいと思っているんですね。
——なるほど。減価償却費用について、もう少し知りたいです。
志賀:不動産を買うときは、通常、土地と建物を同時に買うことになります。土地は価値が下がりませんが、建物は時間とともに価値が下がります。そこで耐用年数に応じて購入した価額を少しずつ経費計上が出来るというのが、減価償却の考え方となります。購入した初年度は建物の購入代金を払っているのに、全額経費にならないのですが、二年目以降は支出がなくても経費が発生していくということになります。建物には定額法という償却方法で減価償却を行っていきます。定額法は、その名の通り、毎年、一定額を経費にする方法です。新築は鉄骨鉄筋造(RC造)で47年。鉄骨は重量鉄骨造で37年、軽量鉄骨造で17年、木造は22年になっています。中古物件は耐用年数から購入時の経過年数を引き、経過年数の2割が乗ります。たとえば、法定耐用年数が30年で、経過年数が10年の中古物件の耐用年数は次のようになります。
(1) 法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数
30年-10年=20年
(2) 経過年数10年の20%に相当する年数
10年×20%=2年
(3) 耐用年数
20年(1)+2年(2)=22年
ということで、22年の償却になります。仮に物件が2200万円であれば、毎年
100万円ずつ経費にして、22年で償却するということになります。
建物を定額法で全部取ってしまうと、減価償却費が非常に少ないので、最初からデッドクロス状態になりやすい。そこで、設備を減価償却費に入れる人が多いのです。通常、建物と設備を区分けして、設備に関しては定率法が選べるかたちになっている。定率法を選択すると、年数にもよりますが、定額法の倍以上が初年度の経費で落とせることになります。ただし、あくまでもこれは経費の先取りであって、定率法だからトクをするという話ではありません。
——設備というのは、具体的にいうと何ですか?
志賀:設備は、給排水設備とか、エレベーターなどですね。通常、中古物件を購入するときには、建物はいくらで、設備はいくらと内訳が明示されているわけではありません。ですので、厳しい税理士になると、給排水設備は計算ができないので、設備を減価償却で取ってはいけませんという人もいます。しかし、一方で給排水設備は2〜3割取ってもいいという税理士もいます。サラリーマン大家さんの皆さんはどちらが正しいかときかれますが、それはグレーな部分です。法律上は計算ができなければ設備を取らないほうがいいですが、設備がないってのも、現実的にちょっとおかしい気もするので、皆さん次第ですね。一般的な話でいえば、最初からデッドクロス状態になるのをさけるために今は設備の減価償却を取っている人が多いですね。
【PR】DVD教材 プロから学ぶ 不動産専門税理士が本音で語る「最新税務事情」と「正しい節税術」
ご存知の方も多いかもしれませんが、不動産投資の過熱に伴い、税務当局が不動産投資家を見る目は益々厳しくなっています。これまで見過ごされていたような細かい誤りも、つぶさに指摘されることが多くなったのです。このDVDでは、あなたがそのようなトラブルに巻き込まれぬよう、税務に関する大事なポイントを分かりやすくお伝えします!
税理士に方針を伝えることは重要
——税理士によって対応が違うなんて、難しいですね。
志賀:税金は、ハッキリわかる真っ黒と真っ白な部分は、それぞれ1割ぐらい。
残りの8割の判断はグレーゾーンです。頑固な税理士かそれとも、柔軟に対応ができる税理士かどうかは、どっちが正しいかというのではないんです。なので、最初に頑固な税理士なのか、それとも柔軟に対応できる税理士なのかを調べるのが大事ですが、最初から調べるのは難しいので、税理士に方針を伝えることをオススメします。たとえば、危ないことは一切やりたくないとか、リスクを取りますと伝える。方向性が違うので途中で税理士を変えるということもよくあることです。何も言わなければ、その税理士の得意なやり方でやってしまうことになります。私のイメージでは、古い税理士さんほど固い人が多いなという印象がありますね。なぜかというと、業界用語には納税者不利というのもあり、迷ったら税金を多く払わせようというのがある。グレーな部分は納税者が多く払うようにすれば税務署からつつかれることはありませんので、そうするというのもあります。こういう考え方をする税理士もいるんです。
——なるほど。他に注意すべき点はありますか?
志賀:インターネット上では脱税ぎりぎりまで節税を行ったほうがいいというのが受けがいいので、そういうことをアピールしている税理士もいます。あくまでも税理士の方針なんだということを理解しないと、納税者が知らないうちに脱税ギリギリの節税をやっていることがあります。しかし、そのような節税方法を採用して、罰を受けて罰金を払うのは納税者ですので、そういうことがあるということは注意したいですね。
——ちょっと話が減価償却の話に戻ってしまいますが、建物と設備の内訳というのは、何で確認ができるのでしょうか?
志賀:売買契約書で確認をします。法律上は契約書に明記することになっていますが、明記されていない場合や建物でなく、土地の割合が多く書かれている場合もあります。そうすると減価償却費を計上できる割合が少なくなって、デッドクロスになりやすい。なぜ土地の割合が多く書かれているかというと、売るほうは、建物の割合が多いと建物の消費税がかかるので損をするわけです。土地なら消費税はかからないので、売主は、土地が多くて建物が少ないほうがいい。買主は逆ですよね。何も言わないと売主に有利になっている場合があるので、売買契約書では、そこを必ずチェックして欲しい、と思います。買った瞬間に減価償却費がどれだけ計上できるのかが決まってしまうんです。
たとえば、総額1億で土地と建物が半々とか。契約書に記載してもらえるようにする。税金の計算は合理的な按分で行うことと書かれているだけで、何が合理的かというのは書かれていません。ですが、判例で最高裁まで行ったケースで、固定資産税の評価額で按分するのがもっとも合理的だろうと言われています。税務署と揉める場合は、固定資産税の評価額が基準になるのが一般的です。
もちろん、おかしな按分でなければ、当事者同士が合意した金額というのが一番強いというのが原則ですが、常識的な範囲内であれば契約書に書いたものが一番強い。それが何十年も減価償却に影響してくるので、購入の際には気を付けてください。
——ある不動産会社では、物件の内訳が、建物が7割、土地が3割という構成になっていました。このようなことはあるのですか?
志賀:固定資産税の評価額できちんと割合を出しているかということが重要なんです。固定資産税評価額からあまりにもかけ離れた割合で売買契約を結ぶのは危険だと思います。たとえば、固定資産税評価額の建物の価値が6000万円、土地の価値が4000万円なのに、建物の価値を9000万円にして、土地を1000万円にして売買契約を結ぶのは無理があります。なかには売買契約書に書いてしまえば大丈夫だという人もいますが、それは法律的に大丈夫なのではなくて、税務署が見逃してくれるのではないかという判断に基づくものです。
私が関わった案件で固定資産税評価額が建物5割、土地5割の物件がありました。これを売買契約書上、土地2000万円、建物8000万円購入したことにしてもいいかと聞かれました。私は調査が入ると危険だとその方に注意をしたのですが、その方の判断で契約書をそのように書いてしまった。結局、税務署に指摘されることになりました。理由は契約書には土地の割合が2割、建物の割合が8割と書かれていましたが、合理的な方法で按分をされていないということです。あとは、たとえば耐用年数が切れている木造建築の物件の場合、4年で減価償却をすることができます。木造の法定耐用年数は、22年ですが、22年以上経過している物件の場合は、法定耐用年数22年×20%=4.4年(少数点切り上げ)で 、4年で償却ができます。法定耐用年数が切れた木造建築を節税のために購入する方法は昔からありますが、土地と建物の割合があまりにもおかしいと知らず知らずのうちに脱税になってしまいますので注意が必要です。
【PR】DVD教材 プロから学ぶ 不動産専門税理士が本音で語る「最新税務事情」と「正しい節税術」
ご存知の方も多いかもしれませんが、不動産投資の過熱に伴い、税務当局が不動産投資家を見る目は益々厳しくなっています。これまで見過ごされていたような細かい誤りも、つぶさに指摘されることが多くなったのです。このDVDでは、あなたがそのようなトラブルに巻き込まれぬよう、税務に関する大事なポイントを分かりやすくお伝えします!
——減価償却は、定額法ではなくて、事業当初に多額の経費を計上でき、節税できる定率法を選んだ方がいいという話もあります。
志賀:減価償却を定率法で早く取る、または修繕費をすべて経費にすることは、長期に渡って経費に計上する分を、短期で経費に計上するということです。定率法を選択したからといって、節税になりますというのはちょっと間違っていますね。たしかに定率法を採用して減価償却をすれば、償却費は初年度ほど多くなります。ただし、年月とともに経費にできる部分が少なくなるので、当然税金が高くなってしまい、キャッシュフローに影響が出てきます。
一方で、初年度で節税をやり過ぎて赤字の申告をすれば融資の審査が通りにくくなります。もちろん、赤字にすれば青色申告控除は使えなくなりますから、その分、所得を減らすことができなくなります。他にも不動産所得が赤字になると、借入利息のうち、土地を購入するときに必要になったローンの金利部分は必要経費として計上できなくなります。一生懸命、経費を増やしたのに、一方で経費にできない部分も出てくる。節税といってもただやればいいというわけではありません。長期的な視点で節税を考える。だから、減価償却をあえて長い期間とるのも選択肢のひとつになるんですね。
——減価償却資産の具体的な経費の仕方について教えて下さい。
志賀:減価償却資産といっても、建物や設備などいろいろありますが、今回は20万円〜30万円までの小額の設備について紹介しましょう。方法は3つあります。ひとつは、①即時償却という方法です。たとえば、エアコンが18万円するとします。青色申告を行う場合は、減価償却資産が30万円未満の場合は、即時償却といってその事業年度ですべて償却する、経費にすることができるんです。
もうひとつは、②一括償却資産で処理をするやり方です。10万円以上、20万円未満の減価償却資産の場合、一括償却資産で処理をすることができます。これは取得価格を3年間に渡って均等に費用にしてくやり方です。エアコンの取得価格が18万円ですから、それを3等分すると6万円。つまり、1年間で6万円ずつ経費にしていく方法になります。
最後は③通常の減価償却の方法です。エアコンは6年で償却すると法律で決まっているので、1年間で3万円ずつ経費にしていくことになります。この3つの減価償却の方法ですが、どれを選ぶのも自由です。赤字になって経費をムダにしたくないということであれば、一括償却資産で処理する方法や通常の減価償却で処理する方法がいいでしょう。税理士にこれらのことをきちんと指示をしないと、一般的な税理士は即時償却の方法を採用します。税理士は税金を減らすのが仕事ですし、そもそも税理士試験が今年度の税金をいかに減らすかということを前提として行うので、2年目以降の税金は関係ないのです。赤字にしたくないので、即時償却以外の方法でお願いするなど自分でコントロールをするようにしてください。
——赤字というと税金が少なくなったり、場合によっては還付を受けたりして、メリットだけのように思えますが、違うんですね。
志賀:そうですね。融資の評価が悪くなるということですね。
【PR】DVD教材 プロから学ぶ 不動産専門税理士が本音で語る「最新税務事情」と「正しい節税術」
ご存知の方も多いかもしれませんが、不動産投資の過熱に伴い、税務当局が不動産投資家を見る目は益々厳しくなっています。これまで見過ごされていたような細かい誤りも、つぶさに指摘されることが多くなったのです。このDVDでは、あなたがそのようなトラブルに巻き込まれぬよう、税務に関する大事なポイントを分かりやすくお伝えします!