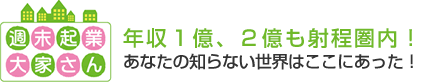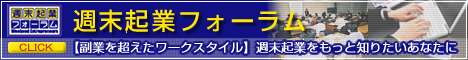不動産投資の初心者が知っておきたい節税対策と税務調査への心構え 【税金コラム02】
このコラムは、不動産投資専門税理士の志賀公斗先生に行ったインタビューをもとに作成しております。
不動産でお金を稼ぐことと同じぐらい、税金対策は必要
——不動産投資ではオーナーとして賃貸業に力を入れるだけではなく、節税にも目を向けようと志賀先生は提言していますね。それはなぜですか?
志賀:節税をしなければ、お金が残りにくいからです。たとえば、あるサラリーマン大家さんが不動産投資で500万円の利益を出したとしましょう。給料と合わせれば所得税の最高税率が掛かってしまう場合、税金対策をしなければ、半分が税金で取られてしまいます。しかし、税金対策をしっかり行うことができれば、手元にそのお金を残すこともできるのです。不動産投資で稼ぐことは、当然ですが、それと同じぐらい税金対策が必要なのです。しかも、一度、節税できる仕組みさえ作ってしまえば、毎年同じだけの節税効果を見込めることができます。家賃収入を毎年100万円増やすよりも、毎年100万円税金が安くなる仕組みを作る方がはるかに簡単なのです。
——具体的にはどのような節税方法があるのでしょうか?
志賀:不動産投資の節税対策は大きく分けて3つあります。ひとつは、お金を使う節税になりますが、「①経費を増やす節税方法」です。もうひとつは、青色申告特別控除や、小規模企業共済等掛金控除など「②控除を増やす節税方法」です。具体的には、修繕や接待、セミナー代など経費を増やして、不動産所得を減らすことで節税します。最後は、そもそもの「③税率を下げるという節税方法」です。たとえば、配偶者を役員にして所得を分散したり、法人化して所得分散をしたりすることで税金を節税します。サラリーマン大家さんには、最終的に仕組みをつくって節税する方法を考えていただきたいと思っています。
もちろん、仕組みを作るまでには時間もかかりますし、労力もかかります。だから、節税というとお金を使って節税する経費で節税しようという考え方に流れてしまいます。
一方で経費を増やして節税をすると、税金は確かに安くなりますが、利益が残らないので融資が通りにくくなってしまいます。融資が通りにくくなれば、次の収益物件を購入することができなくなり、不動産の収益だけで生活するという夢も出来なくなる可能性があるのです。税金が安くなる仕組みを一度作ってしまえば、毎年税金を安くすることができます。だからこそ、仕組みづくりを優先して欲しいですね。
——なるほど。では、まず仕組みづくりからですね。
志賀:税率を低くする仕組みを作るためには、不動産の購入時に行う必要があります。個人で購入した不動産を法人へ所有移転すると、法人は別人格なので再度登記費用や不動産取得税などの税金がかかります。そうした諸費用は物件の1?2割程度でバカになりません。ですので、不動産購入前に準備をしておくことが大切です。
——控除を増やす節税方法については、何か注意点がありますか?
志賀:個人で不動産投資をスタートすれば、最初は当然、白色申告になっているので青色申告の承認申請手続きを行わなければなりません。ただし、手続きには、〆切がああります。〆切は青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までになります。ただし、その年の1月16日以後に、新たに事業を開始したり、不動産の貸付けをしたりした場合には、その事業開始などの日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内に提出する必要があります。間違ってはいけないのが、確定申告の翌年の3月ではないということ。2015年の5月に初めて不動産を買った人は、2カ月以内ですから7月までに出せばいい。ところが今までワンルームを買っていた方が青色申告をする場合には、3月15日までに出しておかないと青色申告できない。こういったことは収益物件を持つ前から実行することができます。いずれにしても節税の仕組みを作るためには、税理士の相談を後回しにしないで、最初から相談するということを忘れないようにしましょう。購入前の対応で不動産投資の節税は半分以上決まってしまうということを覚えておきましょう。経費の計上も重要ですが、それ以上に効果の大きい節税法を取ってもらいたいと思います。
【PR】DVD教材 プロから学ぶ 不動産専門税理士が本音で語る「最新税務事情」と「正しい節税術」
ご存知の方も多いかもしれませんが、不動産投資の過熱に伴い、税務当局が不動産投資家を見る目は益々厳しくなっています。これまで見過ごされていたような細かい誤りも、つぶさに指摘されることが多くなったのです。このDVDでは、あなたがそのようなトラブルに巻き込まれぬよう、税務に関する大事なポイントを分かりやすくお伝えします!
経費を使って節税をする、その方法
——お金を使う節税方法である経費について教えて下さい。不動産投資では一般の事業と違って使える経費が限られているような気がします。
志賀:経費として認められるのは、税務上のルールとしては「不動産収入を得るために支出した金額」とされています。
具体的には、
①不動産にかかる固定資産税や金利
②水道光熱費などの直接費用
③賃貸にかかる管理費などの一般管理費
④不動産と牛の勉強のためのセミナー参加費
⑤不動産投資の書籍購入費用
⑥物件視察のための交通費
などです。よく「どこまでが経費になるか?」という質問を受けるのですが、この質問の真の意図は、「どこまでは、経費に入れてしまっても大丈夫ですか?」という意味合いで質問をされているのだと思います。たとえば、友人と飲み食いをした経費を「接待交際費」で計上してもいいかどうか、私的な名目で使った交通費を「旅費交通費」で計上していいかどうかなどですが、税法上の観点から考えると、不動産投資のための支出でなければ、これらは経費にすることはできません。あくまでも、不動産収入を得るための支出に限られるからです。
——難しいですね。明確な線引きがあればわかりやすいのに。
志賀:そうですね。たとえば、国税庁のホームページには経費の基準についての記述があるのですが、真っ黒と真っ白の事例しか掲載されていません。でも、実務はグレーが8割なので、ホームページは参考程度にしかなりません。税務署は税金対策なんてしてくれません。ただ、申告書が出ていればいいんです。確定申告の時期には、確定申告書や決算書の書き方を税務署で教えてくれるサービスが展開されています。しかし、これには要注意。
税理士業界には“納税者不利”という業界用語があります。これは経費計上をするときに、グレーなことで判断に困ることがあれば、納税者に多く払わせるような原則の判断基準を適用しなさいということです。
——サラリーマン大家さんは、どのようなものの経費計上が多いのですか?
志賀:車の減価償却や維持費用について、どこまで経費に認められるかという相談が多いですね。不動産投資で100%使っているというのは、まれで家族旅行などにも活用している方が多いのですが、その場合、何割を不動産収入を得るために使って、残りの何割を私用で使ったという按分をしなければなりません。その際に何割が不動産投資に使ったかということを客観的に証明しなければなりません。ドライブレコーダーのようなものを車内に設置して走行記録をつけて測定する方法もあります。しかし、面倒ですから半分を経費にしている人が多いですね。ところが、不動産投資の割合を8割にすると税務署から指摘されやすいんです。税務署によって言うことが違うのですが、サラリーマン大家なら土日しか乗らないので、不動産投資には7分の2だろうとか、近場なので電車でいけとか、結局、グレーゾーンの話なので、こういうのは逆にいえば交渉ができる範囲になります。
最終的に2分の1以上で解決したケースもあります。それができた理由は、実際に物件へ清掃状況を身に行ったという記録として残っていた。だから、実態づくりですね。
——よく、領収書をもらっておけということがありますが……。
志賀:領収書などの帳票類は、確定申告後、保管しなければいけない義務があります。期間は7年になっているのできちんと保管をしておきましょう。後になって税務署から連絡があり、このときの取引を提示して欲しいといわれても帳票類が保管されていなければ最悪の場合、否定されることもあります。領収書ではなくて、レシートでもいいのかといわれるのですが、実はレシートのほうがいいんです。名義も関係ないです。税務署が気にするのは日付、金額、経費を何に使ったか、レシートが出ないオンラインショッピングであれば、プリントして取引した証拠を残しておきましょう。
——後は税務署から指摘されやすい経費として、どのようなものが多いのでしょうか?
志賀:家族で飲食したもの、家族旅行をしたものを交際費で落とすケースですね。不動産所得では、交際費はすべて落ちないのかというとそうではなくて、業者の接待であれば十分、交際費として認められます。しかし、記録をきちんとつけておくことが必要です。物件視察に行った場合でも、現地できちんと見て来たという記録を残せば認められます。
また、家族旅行を福利厚生費で経費計上しようとする人が多いのですが、役員や従業員が家族の場合は、福利厚生費は法人でも認められません。法人でも認められていないぐらいですから、個人事業の場合は言わずもがな、です。
——そのほかに経費による節税で注意すべきポイントはありますか?
志賀:皆さんはお金を増やしたいのが目的であり、税金を減らしたいのが目的ではないということ。これを忘れてはいけないと思います。「あと、いくらまで経費を使っていいのですか?」と聞かれることが多いのですが、そのような考え方は投資家として間違っているような気がします。気持ちはわかりますけれども。たとえば、税金で200万円を払わなければいけなくなったからといって所得を1000万円減らすために不動産会社を1000万円分接待したというのは、ちょっとおかしいかなと思います。税金を払いたくないので海外に物件を見に行こうというのは、本末転倒。投資として利益はあげるのが大事で、本来、経費は少ないほうが健全経営ですよね。
——税金は投資の一部という考え方で払っている投資家もいます。
志賀:税金も経費のひとつという考えかたはありです。無駄遣いをするよりも払ったほうがいい。経費を一杯使って、赤字にしておくほうが税金対策にはなりますが、お金を貸す金融機関から見れば、放漫経営をしている会社としてしか見られません。とてもお金を貸す気になれないでしょう。ですので、融資を考えているのであれば黒字にした方がいいのです。税金対策をすればするほど、融資条件は悪くなります。税金は融資に対しての経費だと考えていただきたいですね。そうすると、税理士への態度も変わって来ます。一般的な税理士は、税金を減らすことしか考えていません。だから、ある程度、税金も払って融資を受けられるような状態にしておきたいと伝えておかなければ、融資が受けづらい決算書になってしまいます。細かいところは税理士に任せてもいいのですが、全体の方針は伝えたほうがいいですね。
あとは、サラリーマンをやりながら不動産投資をしている場合、赤字で確定申告書を作成すると、会社に連絡がいってしまうんです。確定申告書の2面に、住民税の普通徴収を選ぶ欄があります。多くの本ではそこにチェックを入れておくと、勤め先に連絡はいかないと書かれてます。しかし、赤字だと会社に連絡がいってしまうんです。そういう面を考えても黒字にしておいたほうがいいと思います。
【PR】DVD教材 プロから学ぶ 不動産専門税理士が本音で語る「最新税務事情」と「正しい節税術」
ご存知の方も多いかもしれませんが、不動産投資の過熱に伴い、税務当局が不動産投資家を見る目は益々厳しくなっています。これまで見過ごされていたような細かい誤りも、つぶさに指摘されることが多くなったのです。このDVDでは、あなたがそのようなトラブルに巻き込まれぬよう、税務に関する大事なポイントを分かりやすくお伝えします!
泣く子も黙る、税務調査
——税務調査について教えて下さい。伊丹十三さんの映画『マルサの女』みたいな感じで、現場に踏み込んでガサ入れしたり、内偵調査みたいなものも入るんですか?
志賀:税務調査とひと言にいっても、強制調査と任意調査という2つの種類があるんです。映画は前者ですが、一般的には税務調査といえば、後者。納税者の立ち会いの元に、帳簿書類を税務署員が任意で調べるというのが普通ですね。
——具体的にどのような順序で税務調査が行われるのでしょうか?
志賀:まず、税務署から「お尋ね」という文書が送られてきます。お尋ね文書の書き方もいやらしくて「間違いがあると思うので確認してください」という内容です。税務署は納税者自らの修正申告を迫る形で文章を作成します。納税者も多少なりとも後ろめたいところがあることもあるので、修正申告に応じてしまうことが多いですね。
ところが、そういう態度を取るということは税務署に間違いを認めたということになります。自分の間違いを認めて修正したということになるので、後ほど自分で間違いに気づいても訂正することができません。だから、税務署からお尋ねが来ても、自分で間違っていないと思ったら修正申告をする必要がないのです。それでも税務署が間違いだと思うのであれば、強制的に申告書を訂正してきます。これが更正処分になります。更正処分に納得できなければ裁判になるのですが、税務署も時間がかかるので裁判にしたくない。たとえば、本当に経費として使ったものかわからないと税務署で指摘されても、個別に経費かどうかの明確なルールがあるわけではないんです。でも、本当に経費に使ったのであればとことん戦うべきでしょう。しかし、それを自分自身でやるのは大変なので税理士に間に入ってもらうのがいいと思います。グレーなものであれば、裁判の手間とかは税務署とかもいやなので、引く場合もある。3つグレーなものがあれば1つは黒でとか。税務署との対応は交渉になります。
——お尋ね文書はいつ届くんですか?
志賀:4月ごろに来る人もいますし、秋に来る人もいます。人によっていろいろです。ただ、税務署から電話があると気持ちいいものでもないですよね。納税者は税務署は申告を直させるための切り札を持って電話をしていると思っていますが、そうじゃないんです。だから修正申告を迫るわけでもあるんです。
——税務署に目をつけられると、ずっと目をつけられられたりするのでしょうか?
志賀:一度目をつけられたとしても、悪質でなければずっと目をつけられるということは、ないですね。しかも仮に税務署に目をつけられても3年後にはその職員は転勤でいなくなるので、大丈夫だと思います。昔の税理士は税務署といかに仲良くするかが大きな仕事だったのです。税務署と仲良くして、グレーな案件のうち、いくつかは黒でという譲歩を引き出すのが昔の仕事やり方です。しかし、ある面からみると癒着ですから税務署が対応策を講じた。その結果、税務署の職員の移動のスピードが早くなって、3年同じ税務職員がいることはなくて2年ぐらいになったんです。そうすると、税理士もせっかく税務職員とパイプをつくってもいなくなってしまうということです。
——なるほど。
志賀:税務職員が異動になる場合、自分の案件を他の人に引き継ぎしなければいけないのですが、それを引き継ぐときに、マイナス評価でいやなので、移動の前にもめごとは終わらせておきたい。すると、長引かされるのが一番嫌だ。だから裁判はいちばん嫌なんですね。
——税務署に罰金というのはあるんでしょうか?
志賀:重加算税というのがあって、悪質なケースの場合は4割増しで税金を払うことになります。しかし、一般的には過少申告加算税、たんなる間違いでしたという場合には、50万円までは10%、それ以上は一般的には15%増しで払います。そして、納税期限を過ぎた日数分の利息を支払います。法律上では7年分までさかのぼれますが、悪質でないなら3年分はさかのぼって過少申告加算税がかかるということですね。相談は早いにこしたことはない。1月に不動産を買って、翌年の3月に初めて相談にきたらほとんど対応できません。早期発見、早期治療じゃないですけど、税金対策の選択肢を増やすためにも早めの相談が大事ですね。
【PR】DVD教材 プロから学ぶ 不動産専門税理士が本音で語る「最新税務事情」と「正しい節税術」
ご存知の方も多いかもしれませんが、不動産投資の過熱に伴い、税務当局が不動産投資家を見る目は益々厳しくなっています。これまで見過ごされていたような細かい誤りも、つぶさに指摘されることが多くなったのです。このDVDでは、あなたがそのようなトラブルに巻き込まれぬよう、税務に関する大事なポイントを分かりやすくお伝えします!